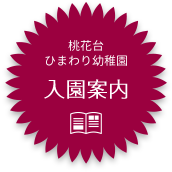-
陶芸 釉薬掛け体験(年長組)
2020年11月12日9月の中旬に3月のお茶会で使うことができるように、自分で抹茶茶碗を陶芸用の粘土を使って作製しました。茶碗作りはそれでおしまいではありません。素焼きした茶碗の表面に釉薬という上薬をかけて生成していきます。今日はその、薬をつける体験をしました。
ぱっと見は、セメント?な感じに見える釉薬に、子どもたちもちょっぴりドキドキ。自分より前にやる子の様子をじっと見つめて、大丈夫なのかどうかを確認している様子が可愛いですね。

「つめた~い!」という子・「ちょうどいいよ~」という子・「あったかいよ。」という子と様々でしたが、みんな同じ釉薬のはずですが、感想はわかれました。粘土で形を作って完成ではなかったんだと、子どもたちも次の作業があることに驚いていました。慎重にそ~っと入れていく子や両手でザバっといっちゃう子などこちらも様々。子どもたちのお手製抹茶茶碗も造形展の日に展示させていただきます。そして、3月のお茶会にはお家の方にお子様お手製の茶碗でお子様がたてた抹茶をいただいてもらう予定ですので、こちらもお楽しみにしていてください。


お兄ちゃん・お姉ちゃんが外で興味津々なことをしているのを窓越しから見ていた年少さん。2年後にはこちらのお兄ちゃん・お姉ちゃん側になっているんだよ~と考えるとまた感慨深くなりました。
さあ、いいな~な顔をして釉薬体験を見ていた年少さんは体操の時間がありました。足を鉄棒にかけて手を離してブラ~ン。年少さんだと怖がりそうな体勢ですが・・・ぜ~んぜん、だ~れも怖がりません。 そのことに友彦先生は驚いています。


自分の番が終わっても、もっとやりたい!もっとやりたい!と、空いている少し高い鉄棒で自分でやり始めていました。

その横では満3歳児の赤帽子さんたちが砂あそびをして楽しんでいました。「ごはんをつくってま~す。」「あたためますのでまっててくださ~い。」などと、もう会話は大人顔負けな店員さんになっていました。その会話がしっかりしすぎていて、それがまた可愛い姿でした。


さあさあ、たくさん遊んで、いろいろな体験をして、お腹が減ってきましたね。今日は、桃花台ひまわり幼稚園の給食の中で、№1といっても過言ではない、『みそラーメン』の日です。


美味しさに思わず、のけぞってしまっていたり、またこの笑顔。どのクラスもおかわりもあっという間になくなっていたようです。廊下を通ると、「せかいいち、おいしい~。」との声が聞こえてきました。そのことを調理員さんに話をすると、涙を流し(大袈裟ですが・・なくらいに)喜んでいました。こちらのレシピは幼稚園がコロナウィルス感染拡大防止の自粛期間にブログに載せていますので、遡っていただくと出てきますのでぜひ、ご家庭でも作ってみてくださいね。明日は、楽しみにしていた遠足です!! わくわくして寝れないかもしれませんが、早く寝て、早く起きて元気に明日、会いましょうね!
-
♪どんぐりころころ どんぶりこ♪
2020年11月11日気候のいい日が続いています。今日も日中はぽかぽかと日差しが入っている中、子どもたちは元気に園庭で遊んでいました。その時、先生が、「子どもたちがかわいい遊びを始めたんですよ~!」と話しをしてくれたので、早速、見に行ってきました。
みんなで大きな山を作って、山の頂上には、どんぐりを置く穴が作ってあり・・・

その頂上から、園庭で拾ったどんぐりを転がします。歌付きで、♪どんぐりころころ どんぶりこ~♪


その後の歌詞は、♪おいけにはまって さあたいへん♪ ちょっと、写真だと分かりにくいのですが、山の横にはちゃんと、池が作ってあって、どんぐりがその歌詞の通りに、転がって、池にはまるように作られていたのです! しかも~、その続きは、♪どじょうがでてきて こんにちは ぼっちゃん いっしょにあそびましょ♪

葉っぱと一緒に落ちてきた長い茎をどじょうに見立てていて、ちゃんとどじょうまで登場していたのです!これまたすごい。子どもたちが歌いながら、その歌詞の通りに遊んでいることに驚きました。おもしろいですね。黄色帽子の年中さんは今日は、体操も頑張っていましたよ!
鉄棒に挑戦です。

ぴょんと跳びあがり、まずは鉄棒の上に小鳥さんのようにとまります、そしてくるっとまわり、今日は忍者のように足を静かに音があまりしないように降りてみましょうに、見本でやってくれた男の子に友彦先生が、「どうやってやったのですか?」の質問をすると、「まわったらあしをゆっくりおとしました。」と、コツまでしっかり話をしてくれました。そして、足をかけて、手を離してみることにも挑戦! これは子どもたち、怖がってしまうのかも~の心配はなく、

こんなにブンブンとしても、


子どもたちからは怖いどころか、「やりたい!やりたい!」の声があちこちから。勇気ある年中さんです。その頃、年長さんは何やら職人モードになって集中していましたよ。


これは、これからの季節にぴったりのクリスマスリースですね!

このリースのベースは幼稚園の砂場の上の藤のつるを使って、子どもたちが丸めたものなんですよ。


どの子のリースも素敵に出来上がっていました。造形展に展示になりますのでお楽しみにしていてください。このまま晴天続きで遠足を迎えられるといいですね!
-
もうすぐお米のできあがりですよ(稲刈り体験 年長組)
2020年11月10日6月にどろんこになりながらお米の苗を植える田植え体験をした年長組の子どもたち。収穫の秋を迎え、稲穂にお米がたくさんついてきました。自分がたちが植えた苗が、ぐんぐんと伸びてお米ができていること、びっくりするだろうなあ。
いよいよ、本日、稲刈りに出かけてきました。 姉妹園の村中保育園の子どもたちも一緒に体験をしている場所です。
保育園に到着してそこから、田まで歩いていきます。
見事に実った稲穂がたくさん。たくさんあるから、みんなで頑張って稲を刈りますよ。稲を刈るのはカマという道具を使います。料理でいうと、包丁のように、刃がついていて使い方を間違えると危険なので、子どもたちがカマを使用することに驚かれるかもしれませんが、年長さんはお米作りをずっと教えてくださっている現地の後藤さんご家族と地元の方々のお話をしっかりきいて、危険な物だときちんとわかってるからこそ慎重に集中して使用して、その手つきのよさに驚きました。
最初は、大人の人が手を添えながら行うとすぐに感覚を覚えて、手を添えようとすると、「ひとりでできるから~。」と。この、「ひとりでできるもん」っていう気持ちが上達していく基なのかもしれませんね。
豊作で、ひとり何束の稲穂を刈ったのかもう数えられないくらいにやっていました。それでも、子どもたちは、「もっとやりたい!」「こっちもやっていいの?」などと、みんな積極的。カマという道具を使いこなせるようになった自信も出てきたようです。現地の方たちにも、「じょうずだねえ。」「おてつだいにきてよ。」などと農家にスカウトされる声もあったり。褒めていただけるとうれしいですよね。
青空の下での稲刈り、子どもたちお天気に恵まれていますね。この調子ですと、親子遠足も大丈夫そうですね。
今日、稲刈りをした稲は少しの間、このように干しておくともっと美味しくなるそうです。次はこの稲を脱穀してお米として食べれる状態に近づける体験に後日また来ます。お米作りを指導してくださっている後藤さんとお手伝いしてくださった地元の方々にも感謝です。どうもありがとうございました。また、おじゃまします。
稲刈りを頑張ったらお腹が減ってきました。今日は、お弁当を持ってきたので村中保育園のテラスで食べてきました。
お弁当を食べた後は、村中保育園の園庭で遊んできました。幼稚園とは違う遊具があったりして、子どもたちはいつもと違う園庭で大はしゃぎでした。
二人で乗れる自転車があるんだ~。おもしろいね。
あれ、いつもは砂場にはあまりいない子が幼稚園とは違う砂場道具があって興味があるのか砂場あそびに夢中だったり。

「これようちえんのより、ちっちゃくてあしがつくよ。」と、雲梯で遊んでいたり。

みんなでバスに乗って出かけて、稲刈り体験をして、保育園の園庭でもたくさん遊んで帰りのバスの中では、暖かい日差しが入り込み、ウトウトとしている子も。思いっきり楽しんで、思いっきり遊んで、ウトウト・・・子どもたち、かわいいですね。
そして、本日は全園児がお弁当の日でした。どの子もみんなお家の方お手製のお弁当大好きです。どうもありがとうございました。
0568-79-1621
お問合わせはこちら